GPSとは
GPSは、人工衛星から受信した情報を受け取り、受信側の現在位置を把握することができる全地球測位システムのことであり、全球規模で位置情報を提供する衛星測位システムです。一般的には英熟語 Global Positioning System(グローバル・ポジショニング・システム)の頭文字をとってGPS(ジーピーエス)と呼ばれています。
GPSは元々、アメリカ合衆国と旧ソ連の冷戦時代に、航空機や船舶の位置情報をリアルタイムで正確に把握するため、アメリカ合衆国が開発した軍事用の技術でしたが、民間利用が広まり、現在では世界中で広く利用されています。
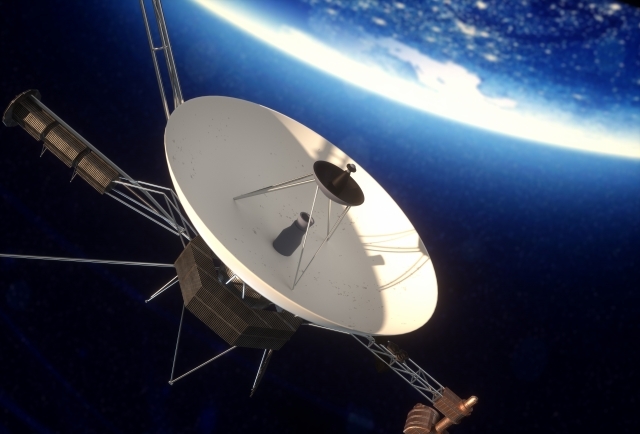
GPSの歴史
冷戦時代にアメリカ合衆国が開発したGPSは、当初は航空機や船舶の位置情報をリアルタイムで把握するための軍事技術でした。しかし、1983年に起こった大韓航空機撃墜事件から、民間機の安全な航行のためにGPSを非軍事的な用途でも使えるよう開放する事をレーガン大統領が決定し、次第に民間利用が広まり普及したといわれています。
GPSの仕組み
地球の周りを回っている約30個のGPS衛星からの信号をGPS受信機で受け取り、受信側の現在位置を正確に知ることができるシステムです。1989年に初の実用衛星を打ち上げはじめ、1993年からGPSの運用開始が宣言されました。
GPSは、衛星自体が対象の位置を正確に把握しているというわけではありません。地球上にある受信機から高度約2万kmの軌道上に配置された「GPS衛星」へ信号を発信し、衛星からその返答が戻るまでのわずかな時間の差を計算することによって地球上の位置を特定できる仕組みです。
その際、1つの衛星を利用するのではなく、4つ以上の複数衛星を使って位置を特定しています。4つ以上の複数衛星を使った位置情報の計算処理自体は、衛星ではなく地球上の端末で行われています。
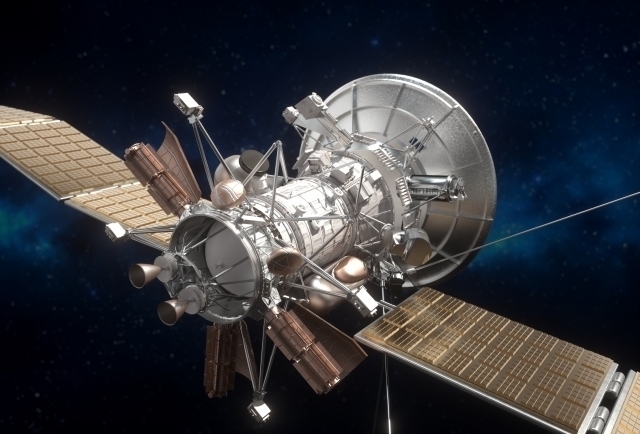
このようにGPSは現在位置をかなり正確且つ瞬時に計測できるため、そのまま技術を公開してしまうことでテロリスト等に悪用されてしまう可能性があり、米国は軍事利用を優先する為に民間用のGPSの精度を落として技術を提供していました。しかし、2000年にこの精度を落とす制限は解除され、測位精度の誤差が約100mから約10mほどに縮まったと言われています。
GPSの拡張
2020年にはアメリカ合衆国以外にも位置情報活用を目的とした衛星を保有しており、ロシアの「GLONASS」、中国の「BeiDou」、EUの「Galileo」、インドの「NavIC」、日本の「みちびき」(準天頂衛星システム)などが有名で、世界各国が独自の位置情報システムを運用しています。
GPSの活用
GPSは、航空・海上、自動車ナビゲーション、スマートフォンの地図アプリなど、様々な分野で利用されています。位置情報を正確に把握することで、航行や移動の効率化、位置情報サービスの提供などが可能となります。
ここまで解説してきたGPSという名称ですが、実はアメリカ合衆国が運用している位置情報測位システムの名称のことを指していて、「人工衛星を使った測位システム」全般を指す名称ではありません。
GPSとGNSS
一般名称としては「GNSS(Global Navigation Satellite System)」(全世界測位システム)という呼び方があります。日本の「みちびき」も厳密に言えば「日本版GPS」という呼び方は実は誤りで、「日本版GNSS」という呼び方が正しいことになります。しかしながら、GPSという名称自体が一般名称化してしまっており、世間一般的に「GPS」と呼ばれています。
位置を捕捉できる衛星が多いほどより精度が上がります。最新の物では20基近くの衛星を使って位置を捕捉できると言われています。
GPSを元にした人流データの活用
クロスロケーションズは、様々なスマートフォンアプリの許諾を得たGPSを収集し、独自のAI技術による人流統計データとして商圏分析やエリアマーケティングに活用しています。位置情報を基にしたリアルタイムなデータ分析により、企業や行政機関は効果的な施策を立案し、効率的な経営や行政活動を行うことができます。
GPSよる人流データに関する詳しい記事はこちらよりご覧ください。



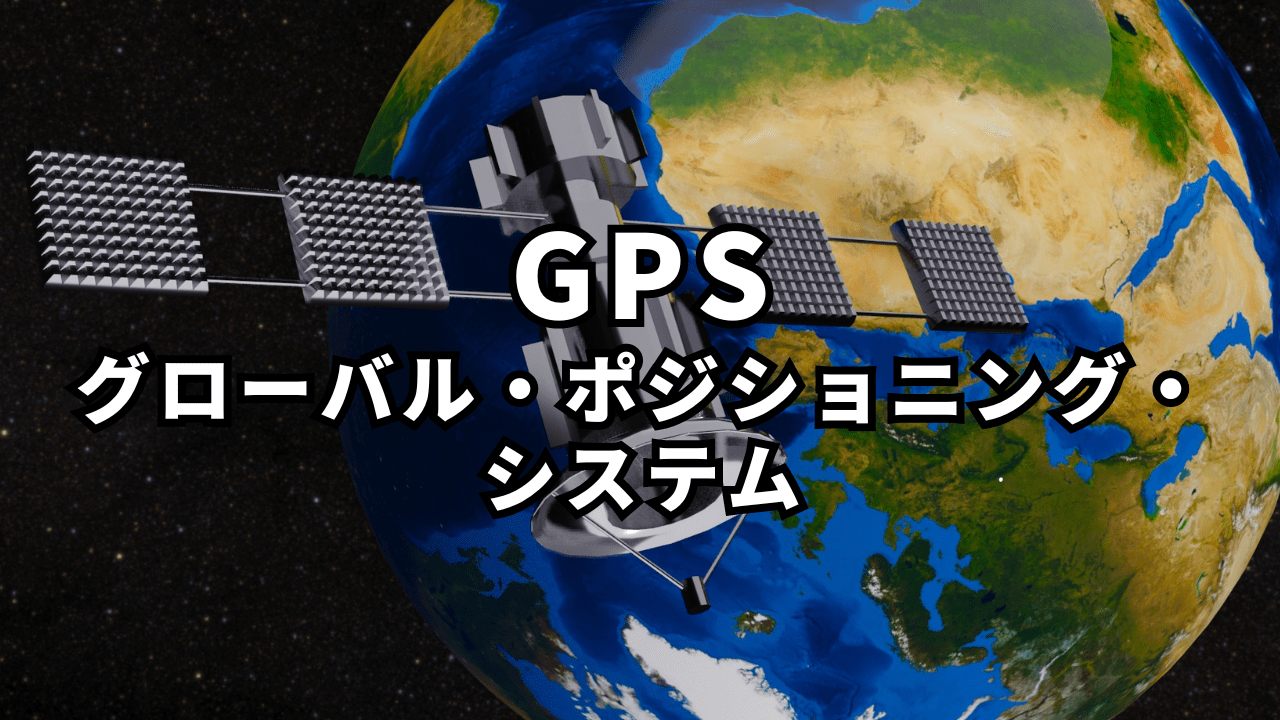


-768x432.png)
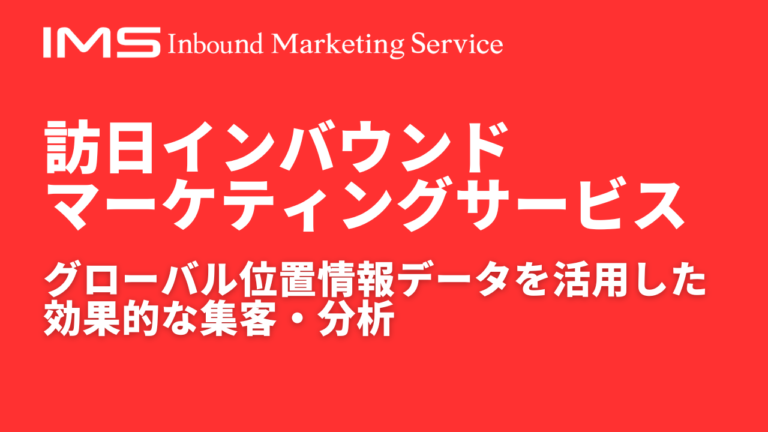

プロモーション_グローバル位置情報データを活用した効果的な施策-min-768x432.png)