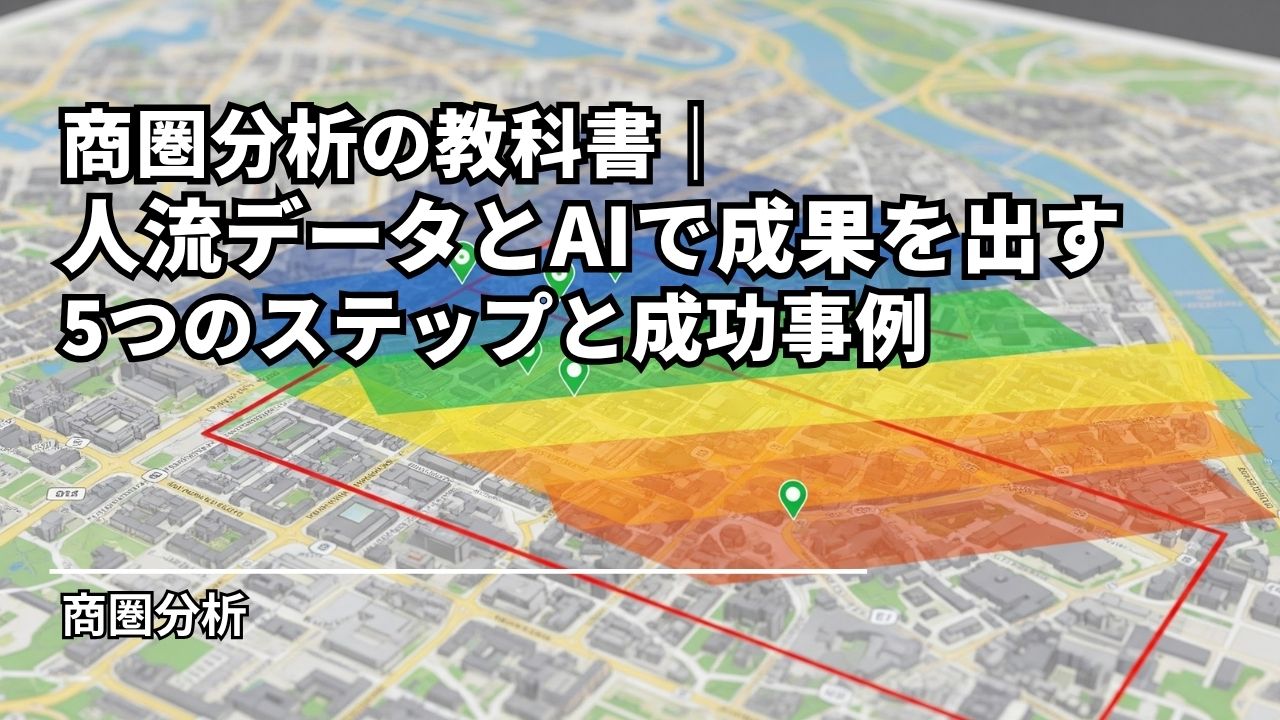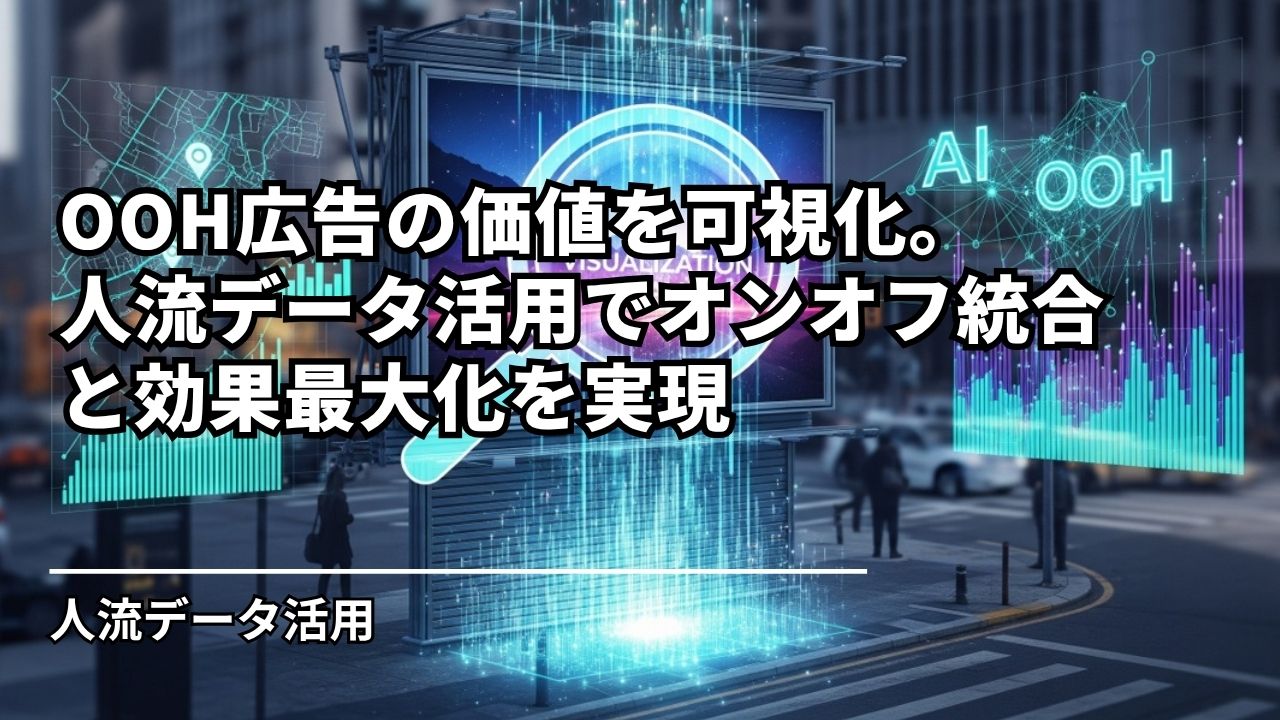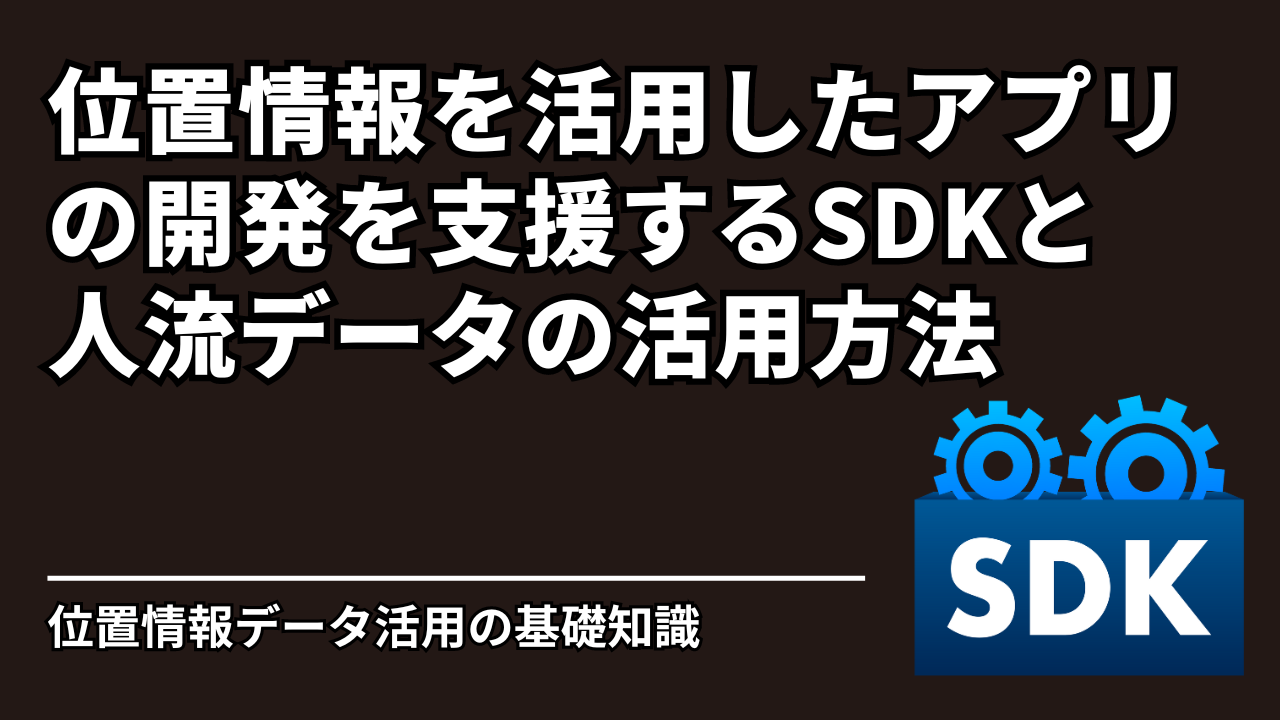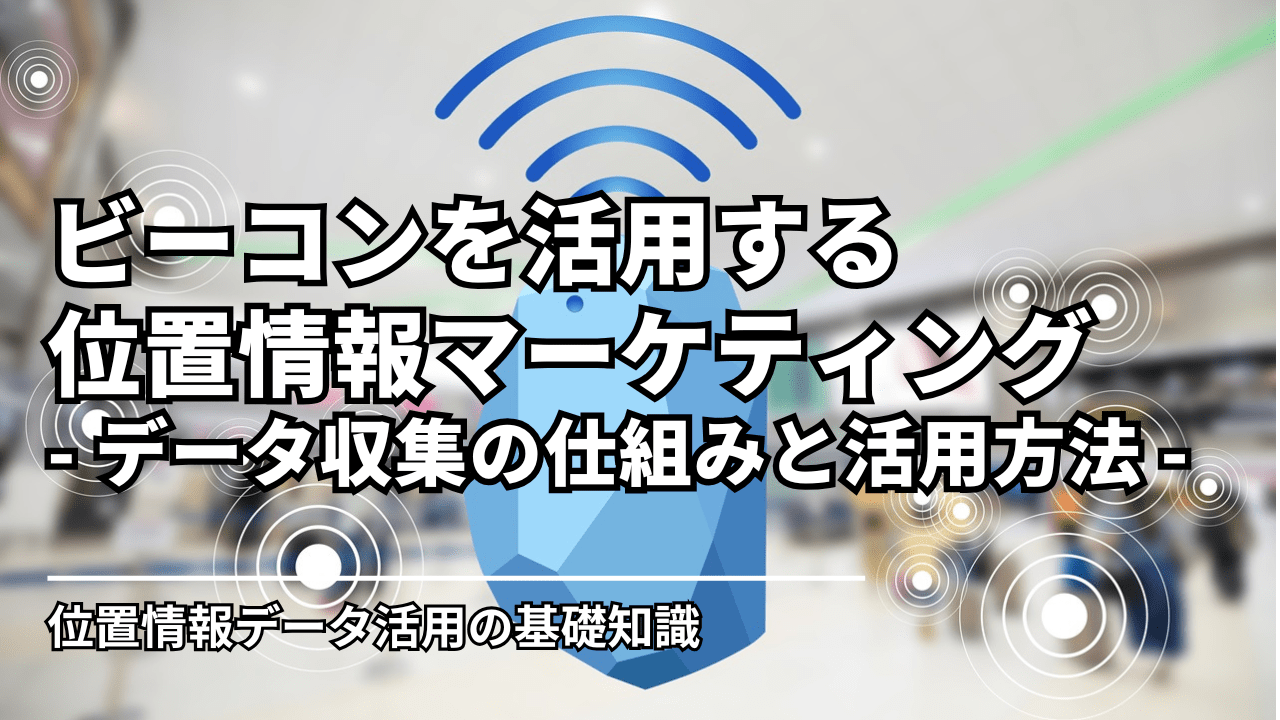店舗の成功を左右する重要な要素の一つに、その地域の特性を深く理解し、戦略に活かす「商圏分析」があります。単に出店候補地を選ぶだけでなく、地域ごとの購買傾向や競合環境、そして実際の人の流れといった多角的な視点を取り入れることで、より効果的なビジネス展開が可能になります。本記事では、商圏分析の基本から、最新の人流データを活用した動的な分析手法まで、分かりやすく解説していきます。
商圏分析とは
商圏分析とは、国勢調査などの統計データや顧客情報を活用して、特定エリアの購買傾向や地域特性を把握するための分析手法です。自社の既存店舗だけでなく、新規出店候補地の評価にも活用され、GIS(地理情報システム)を用いて地図上に店舗位置や検討エリアをマッピングし、様々なデータを重ね合わせることで周辺状況を可視化します。
従来の商圏分析は、人口統計や世帯数といった「静的なデータ」を中心に行われてきました。しかし近年では、スマートフォンのGPS位置情報から得られる人流データを活用することで、「実際にどこから、どんな人が、いつ訪れているのか」をリアルタイムに把握できる「動的商圏分析」が主流になりつつあります。
この動的商圏分析により、従来は見えなかった「平日と休日の来訪者の違い」や「時間帯による顧客層の変化」、さらには「競合店との顧客の重なり」まで、詳細に分析できるようになりました。将来の売上予測や販促効果の測定にも応用され、より精度の高い戦略立案が可能になっています。
商圏分析で「見える化」できること
商圏分析を行うことで、商業施設や小売店、飲食店などは、消費者が日常的に利用している地理的範囲を把握し、様々な定量データをもとに販売戦略や店舗開発に活かすことができます。
特に人流データを活用することで、従来の統計データだけでは把握できなかった実態が「見える化」されます。次に、商圏分析で得られる5つの重要な情報をご紹介します。

新規出店の判断に必要な情報を把握
商圏分析は、新たな出店場所を選定する際の情報収集に役立ちます。出店候補地の周辺に住む潜在顧客の把握や商圏内の競合状況など、様々な地理的情報をもとに顧客の需要を分析して、新規出店の可能性を事前に検討できます。
人流データを活用することで、「候補地Aは平日の昼間に人が多いが、候補地Bは休日のファミリー層が中心」といった、時間帯や曜日ごとの詳細な来訪傾向まで把握できるため、より精度の高い出店判断が可能になります。
顧客の特性と行動を把握
商圏内の顧客の属性(年齢、性別、居住地などの情報)と行動を総合的に分析することで、商品やサービスに対する需要の傾向がより詳細に把握できます。この情報はビジネスにおいてターゲット市場を細分化し、より効果的なマーケティング戦略を構築する基盤となります。
従来の会員データだけでは把握できなかった「非会員の来店客」についても、人流データを活用することで、どのエリアから訪れているのか、どんな属性の人が多いのかを推定できるようになりました。
競合店の影響を把握
競合店がどれだけの影響を持っているのかを、周辺の競合店の特性から知ることができます。人流データを活用することで、「自店舗と競合店の両方を訪れている顧客の割合(カニバリゼーション)」や「競合店の商圏と自店舗の商圏の重なり」を定量的に把握できます。
これにより、競合店がうまく実践している戦略やサービスを参考にして自店舗の強化ポイントを見直すだけでなく、差別化すべき領域を明確にすることができます。
販促戦略の最適化
自店舗が位置する地域の顧客層や購買傾向を明らかにする手段として活用できます。これにより、特定の商品やサービスの需要が高い地域や層を特定し、その情報をもとに効果的な販促戦略、ターゲットに合わせた広告やキャンペーン計画を構築できます。
人流データを活用することで、「この時間帯は学生が多い」「休日はファミリー層が中心」といった詳細な傾向がわかるため、時間帯別・曜日別に最適化された販促施策の実施が可能になります。
売上予測
商圏分析データを活用して、過去の情報から将来の売上を予測し、的確な在庫管理やスタッフ配置などの経営戦略に活かすことができます。特にAIを組み合わせた人流データ分析では、「来月のこの時期は来店客が増加する」といった予測精度が飛躍的に向上し、効果的なビジネス戦略の策定が可能となります。
これらの情報を踏まえて商圏分析を行うことで、事業戦略やマーケティング戦略を検討し、ビジネスをより効果的に展開することができます。
従来の商圏分析が抱える3つの限界
商圏分析は多くのメリットをもたらす一方で、従来の手法には見過ごせない課題が存在します。特に統計データに依存した分析では、変化の激しい現代のビジネス環境に対応しきれないケースが増えています。ここでは、従来の商圏分析が抱える3つの限界について解説します。
限界①:更新頻度の低い統計データへの依存
従来の商圏分析では、国勢調査や住民基本台帳といった公的統計データが主な情報源でした。しかし、国勢調査は5年に1度しか更新されないため、「再開発で急激に人口が増えた」「大型商業施設の開業で人の流れが変わった」といった市場の変化に迅速に対応できません。
特にコロナ禍以降、在宅勤務の増加やライフスタイルの変化により、昼夜間人口の分布が大きく変化した地域も少なくありません。こうした変化をリアルタイムに捉えられない点が、統計データ依存型の商圏分析の大きな限界と言えます。
限界②:理論値と実態のギャップ
従来の商圏分析では、店舗から半径○km圏内、または徒歩・車で○分圏内といった「距離圏分析」や「時間圏分析」が一般的でした。しかし、これらは「来店可能な範囲」を示すに過ぎず、実際の来店客とは大きく乖離するケースが多々あります。
例えば、同じ距離圏内でも、「駅の反対側にある住宅街からはほとんど来店がない」「幹線道路沿いの店舗には遠方からも車で来店する」といった実態は、理論値だけでは把握できません。こうした「実勢商圏」と「理論商圏」のギャップが、出店判断のミスや販促効果の低下を招く原因となっています。
限界③:リアルタイムな変化を捉えられない
ビジネス環境は常に変化しています。新規競合店の出店、再開発プロジェクトの進行、大型イベントの開催など、商圏に影響を与える要因は日々変動します。しかし、従来の統計データベースの分析では、こうした突発的な変化に対応することができません。
「最近自店舗を利用している人はどこから来ているのか」「新しくできた近隣の商業施設の影響は」「競合店の様子はどうなのか」といった、変化し続ける情報をリアルタイムでモニタリングすることが、現代の商圏分析には求められています。
人流データ×AIで進化する商圏分析
従来の商圏分析が抱える限界を解決する手段として注目されているのが、「人流データ」と「AI」を組み合わせた動的商圏分析です。スマートフォンのGPS位置情報から得られる膨大な人流データを、独自のAI解析エンジンで処理することで、これまで見えなかった「人の動き」を高精度に可視化できるようになりました。
人流データがもたらす3つの革新
人流データを活用した商圏分析は、従来手法と比較して3つの大きな革新をもたらします。
①リアルタイム性
統計データの5年に1度の更新に対し、人流データは日次・時間単位で更新されます。「昨日オープンした競合店の影響」や「イベント開催時の人流変化」といった、リアルタイムな情報を即座に把握できます。
②実際の行動反映
理論上の商圏ではなく、「実際にどこから来店しているか」という実勢商圏を可視化できます。これにより、出店判断や販促エリアの設定精度が飛躍的に向上します。
③詳細な属性分析
来訪者の性別、年齢層、居住地エリア、滞在時間、移動経路などを詳細に分析できます。従来の統計データでは把握できなかった「どんな人が、いつ、どのように店舗を利用しているか」という行動パターンまで明らかになります。
Location AI Platform®が実現する「動的商圏分析」
私たちクロスロケーションズが提供する「Location AI Platform®(LAP)」は、高解像度のスマートフォンGPS位置情報ビッグデータを独自に解析したエンジンから得られる人流統計データを活用した分析ツールです。
従来の「静的商圏分析」では、一度設定した商圏範囲は固定的でしたが、LAPの「動的商圏分析」では、時間帯や曜日、季節によって変化する商圏を可視化できます。例えば、「平日昼間はオフィスワーカーが中心で商圏は狭いが、休日はファミリー層が遠方から訪れるため商圏が広がる」といった変動をデータで捉えられます。
さらに、過去の人流データを学習したAI解析により、「今後どのように商圏が変化するか」を予測する機能も搭載。出店計画や広告配信エリアの最適化、都市開発の需要予測など、幅広い分野で未来志向の戦略立案が可能になっています。
ワンクリック実勢商圏レポートの衝撃
2025年5月、私たちは「Location AI Platform®」に画期的な新機能を搭載しました。それが「ワンクリック実勢商圏レポート作成機能」です。
従来、実勢商圏の分析には専門知識を持ったアナリストが数日から1週間程度かけてデータを加工・分析する必要がありました。しかし、この新機能により、店舗の位置情報を入力するだけで、瞬時に以下のような詳細なレポートが自動生成されます。
- 来訪者の居住地分布マップ
- 性別・年齢層の構成比
- 曜日別・時間帯別の来訪傾向
- 競合店との顧客重複率(カニバリゼーション分析)
- 周辺ランドマーク施設との比較
この革新により、商圏分析の民主化が実現。専門知識がなくても、店舗運営者や出店計画担当者が自ら迅速に商圏を把握し、戦略立案に活かせるようになりました。
業界別|人流データ活用の成功事例
人流データを活用した商圏分析は、様々な業界で実際に成果を上げています。ここでは、業界別の具体的な活用シーンと、私たちクロスロケーションズが支援させていただいた導入事例をご紹介します。
小売業|実勢商圏で出店精度を劇的に向上
群馬県を中心に展開するスーパーマーケットチェーン「株式会社ベイシア」では、テナント誘致における相互集客効果を人流データで検証しました。ワンクリック実勢商圏レポート機能を活用することで、候補テナントと自社店舗の顧客層の重なりや、相乗効果が期待できるエリアを短時間で特定。
その結果、出店判断のスピードと精度が大幅に向上し、テナントミックスの最適化により売上向上を実現しました。従来は「勘と経験」に頼りがちだった出店判断が、データに基づく客観的な意思決定へと進化した事例です。
飲食業|時間帯別人流で売上を最大化
寿司・しゃぶしゃぶ食べ放題「ゆず庵」を展開する株式会社物語コーポレーションでは、人流データを活用した店舗のカニバリゼーション調査や、店舗ごとの商圏範囲・潜在商圏の可視化に取り組みました。
分析の結果、時間帯別の来訪者動向が明確になり、「ランチタイムは近隣住民が中心」「ディナータイムは遠方からの来店が増加」といった傾向を把握。これをもとに営業時間の最適化やメニュー戦略を見直し、既存店舗の販促施策改善に成功しました。
また、「焼肉きんぐ」や「丸源ラーメン」などの複数ブランドを展開する同社では、ブランド間のカニバリゼーションも分析。新規出店時のブランド選定や、既存店舗のリブランディング判断にも人流データを活用しています。
不動産業|開発エリアの将来性を予測
不動産業界では、物件の投資価値を評価する「オルタナティブデータ」として人流データの活用が進んでいます。私たちクロスロケーションズは、不動産関連事業者へのDX支援サービスを手がける株式会社アクティブリテックと共同で、不動産ファンド向けの人流データ分析サービスを開発しました。
導入事例:不動産業界のXR×DX化に貢献する総合不動産テックカンパニー
このサービスでは、建物や敷地単位での人流、周辺環境の人流、属性情報を統計的に分析し、レポート形式で提供します。コロナ禍以前からの時系列推移や来館者の詳細(年代・男女比率、曜日・時間帯別傾向、推定居住地マップなど)、さらに競合物件や周辺ランドマーク施設・最寄り駅などとの比較分析も可能です。
実際の活用例として、香川県丸亀市中心部において人流データを用いた商圏分析が実施されました。来訪者の回遊性や時間帯別のピークを可視化することで、地域商店街の活性化や再開発計画に反映。従来は把握が難しかった都市中心部の人の流れを定量的に捉えることで、投資判断や街づくりにおける基盤データとしても活用されています。
サービス業・観光地|人流データで販促戦略を最適化
横浜中華街発展会協同組合では、人流データを活用した商圏分析により、来訪者の居住地分布や街内での回遊行動を詳細に把握しました。その結果、「どのエリアから観光客が訪れているか」「街内でどのような動線で移動しているか」が明確になり、効果的な販促戦略の立案や街づくり計画に活用されています。
また、西東京バス株式会社では、Location AI Platform®を導入し、平日・休日の人流動向をもとに新路線の開発や既存路線の増便・減便を最適化。観光客や地域住民の利便性向上に貢献しました。交通事業者にとって、人流データは路線計画の精度向上と収益性の改善に直結する重要な情報源となっています。
商圏分析の実践|人流データ活用の5ステップ
商圏分析を効果的に実践するためには、どのようなステップで進めていけば良いのでしょうか。ここでは、人流データを活用した商圏分析の具体的な進め方を5つのステップで解説します。
ステップ①:目的設定と仮説構築
商圏分析を始める前に、まず「何のために分析するのか」という目的を明確にすることが重要です。新規出店のための候補地選定なのか、既存店舗の売上改善なのか、販促エリアの最適化なのか。目的によって必要なデータや分析手法が変わってきます。
さらに重要なのが「仮説構築」です。例えば、「候補地Aは駅近だが競合が多いため、少し離れた候補地Bの方が実は有望ではないか」といった仮説を立てることで、データ分析の方向性が定まり、より深い洞察が得られます。
人流データを活用する最大のメリットは、こうした仮説を定量的に検証できる点にあります。勘や経験だけでなく、データに基づいた客観的な意思決定が可能になります。
ステップ②:人流データで実勢商圏を可視化
従来の商圏分析では、店舗から半径○km圏内といった「距離圏」や、徒歩・車で○分圏内といった「時間圏」を設定するのが一般的でした。しかし、これらは理論上の商圏であり、実際の来店客の分布とは異なることが少なくありません。
人流データを活用することで、「実際にどこから来店しているか」という実勢商圏を可視化できます。Location AI Platform®の「ワンクリック実勢商圏レポート」機能を使えば、店舗の位置情報を入力するだけで、瞬時に来訪者の居住地分布が地図上に表示されます。
この実勢商圏をベースにすることで、出店判断や販促エリアの設定精度が飛躍的に向上します。
ステップ③:顧客属性と行動パターンの分析
実勢商圏が把握できたら、次は「どんな人が、いつ、どのように来店しているか」という顧客属性と行動パターンを詳しく分析します。
人流データでは、以下のような情報を取得できます。
- 性別・年齢層:来訪者の性別・年代構成
- 居住地エリア:都道府県別、市区町村別の分布
- 来訪時間帯:曜日別・時間帯別の来訪傾向
- 滞在時間:店舗やエリア内での滞在時間
- 移動経路:来店前後の立ち寄り先
Location AI Platform®では、これらの情報をヒートマップやダッシュボードで視覚的に把握できるため、専門知識がなくても直感的に理解できます。
例えば、「平日昼間はオフィスワーカーが中心だが、休日はファミリー層が増える」「20代は短時間滞在だが、50代以上は長時間滞在する傾向がある」といった具体的な傾向が見えてきます。
ステップ④:競合との差別化戦略の立案
商圏内の競合店舗との関係性を把握することも、商圏分析の重要な要素です。人流データを活用することで、以下のような競合分析が可能になります。
クロスビジット分析
自店舗と競合店の両方を訪れている顧客の割合を可視化します。これにより、「競合店の顧客をどれだけ取り込めているか」「逆にどれだけ流出しているか」を定量的に把握できます。
カニバリゼーション分析
複数店舗を展開している場合、自社店舗同士で顧客を奪い合っている状況を「カニバリゼーション」と呼びます。人流データで各店舗の実勢商圏を可視化することで、適切な店舗配置や、新規出店時の既存店への影響を事前に予測できます。
これらの分析結果をもとに、「この時間帯は競合に優位性がある」「この顧客層では差別化できている」といった具体的な戦略を立案できます。
ステップ⑤:継続的モニタリングとPDCA
商圏分析は一度行って終わりではありません。市場環境は常に変化しているため、定期的なモニタリングが不可欠です。
「新しい競合店がオープンした」「再開発で周辺環境が変わった」「販促施策を実施した」といったタイミングで、人流データを確認することで、その影響を定量的に把握できます。
Location AI Platform®では、ダッシュボード機能により、継続的に商圏の変化をモニタリングできます。これにより、施策の効果を測定し、次のアクションにつなげるPDCAサイクルを高速で回すことが可能になります。
商圏分析の効果を最大化するには、この「継続的なモニタリング」が何よりも重要です。
商圏分析において重要な「商圏」の考え方
商圏分析を語る上で、避けて通れない重要な概念が「商圏」です。これは、消費者が生活や購買の際に利用する店舗や施設の地理的範囲を指し、戦略の出発点となります。
従来の商圏分析では、統計データを基にした「静的な商圏」が主流でしたが、現在では人流データとAIを活用することで、時間や状況に応じて変化する「動的な商圏」を把握できるようになっています。次に、この2つの商圏の違いについて詳しく見ていきましょう。
静的商圏vs動的商圏|何が違うのか
従来型の「静的商圏」と、人流データを活用した「動的商圏」には、以下のような違いがあります。
| 比較項目 | 静的商圏(従来型) | 動的商圏(人流データ活用) |
| データ源 | 国勢調査、住民基本台帳など | スマートフォンGPS位置情報 |
| 更新頻度 | 5年に1度(国勢調査) | 日次・時間単位 |
| 商圏範囲 | 固定的(半径○km圏内など) | 時間帯・曜日で変動 |
| 分析対象 | 居住人口 | 実際の来訪者 |
| リアルタイム性 | なし | あり |
| 予測機能 | なし | AI解析により将来予測可能 |
静的商圏は「理論上、来店可能な範囲」を示すのに対し、動的商圏は「実際に来店している範囲」を示します。この違いが、出店判断や販促戦略の精度に大きく影響します。
業態別|最適な商圏設定のポイント
商圏の範囲は、業態や取り扱う商品・サービスによって大きく異なります。以下に、業態別の商圏特性と、人流データ活用のポイントをまとめます。
| 業態分類 | 商圏範囲 | 代表例 | 人流データ活用のポイント |
| 最寄品商圏 | 徒歩圏~1km程度 | コンビニ、ドラッグストア、クリーニング店 | 近隣住民の日常動線を把握。時間帯別の来訪パターンを分析し、営業時間や品揃えを最適化 |
| 買回品商圏 | 車・電車で5~20km程度 | アパレル、家電量販店、家具店 | 広域からの来訪者分布を把握。駐車場需要や滞在時間を分析し、施設設計に反映 |
| 専門品商圏 | 20km以上、広域 | ブランド店、高級百貨店、専門医療機関 | 遠方からの来訪者特性を把握。アクセス手段(電車・車)や来訪頻度を分析し、ブランド戦略に活用 |
| ハイブリッド型 | 時間帯で変動 | 駅前商業施設、郊外ショッピングモール | 平日・休日、昼夜での商圏変動を把握。テナントミックスやイベント企画を最適化 |
人流データを活用することで、これらの業態ごとに最適な商圏設定が可能になります。例えば、同じ飲食店でも「ランチは徒歩圏の最寄品商圏、ディナーは広域の買回品商圏」といったように、時間帯によって商圏が変化することも珍しくありません。
こうした変動を可視化できるのが、動的商圏分析の大きな強みです。
クロスロケーションズが選ばれる理由|他との決定的な違い
商圏分析が行えるツールやサービスは多くありますが、クロスロケーションズの「Location AI Platform®」が選ばれるには、明確な理由があります。ここでは、他との違いについてご紹介します。
従来型GISツール vs Location AI Platform®
多くの商圏分析サービスは、統計データをベースにした「静的分析」が中心です。一方、Location AI Platform®は、人流データとAIを組み合わせた「動的分析」により、実態に即した商圏把握(実勢商圏を把握)を実現しています。
| 比較項目 | 従来型GISツール | Location AI Platform® |
| 分析の基盤 | 統計データ(国勢調査等) | 人流データ(GPS位置情報) |
| 商圏の捉え方 | 静的(固定的な範囲) | 動的(時間・状況で変化) |
| リアルタイム性 | 低い(数年遅れ) | 高い(日次・時間単位) |
| 実勢商圏把握 | 困難(理論値のみ) | 可能(実際の来訪者データ) |
| AI予測機能 | なし | あり(将来の人流予測) |
| レポート作成 | 手動で数日~1週間 | ワンクリックで瞬時 |
| 操作性 | 専門知識が必要 | 直感的な操作で誰でも使える |
クロスロケーションズの3つの強み
①独自のAI解析エンジン「Location Engine™」
高解像度のスマートフォンGPS位置情報ビッグデータを、独自開発のAI解析エンジンで処理。膨大なデータから有益な人流統計データを抽出し、高精度な分析を実現しています。
②ワンクリックで完結する実勢商圏レポート
2025年5月にリリースした新機能により、従来数日かかっていた実勢商圏分析が瞬時に完了。専門知識がなくても、店舗運営者自身が迅速に商圏を把握できます。
③豊富な導入実績と業界別ノウハウ
小売、飲食、不動産、観光、交通など、多岐にわたる業界での導入実績があります。業界ごとの特性を理解したコンサルティング支援により、データを「使える戦略」へと落とし込みます。
単なるツール提供にとどまらず、社会課題やビジネスの成果にコミットしたサービスを提供しています。
まとめ
商圏分析は、特定エリアの購買傾向や地域特性を理解し、それに合わせた戦略を立てる上で非常に有効な手法です。本記事では、商圏分析の基本的な考え方から、従来手法の限界、そして人流データとAIを活用した最新の動的商圏分析まで、幅広く解説しました。
特に重要なポイントは以下の3つです。
①従来の統計データ依存型商圏分析には限界がある
更新頻度の低さ、理論値と実態のギャップ、リアルタイム性の欠如といった課題により、変化の激しい現代のビジネス環境には対応しきれなくなっています。
②人流データ×AIが商圏分析を革新する
スマートフォンのGPS位置情報から得られる人流データと、AI解析を組み合わせることで、「実際にどこから、どんな人が、いつ訪れているか」をリアルタイムに把握できます。これにより、出店判断の精度向上、販促効果の最大化、競合との差別化など、様々な成果をもたらします。
③継続的なモニタリングが成功の鍵
商圏は常に変化しています。一度の分析で終わらせず、定期的にモニタリングすることで、市場変化に迅速に対応し、PDCAサイクルを高速で回すことが可能になります。
効率的な出店戦略、競合との差別化、広告効果の最大化など、様々な成果をもたらす商圏分析において、人流データの活用はもはや欠かせない手段です。
私たちクロスロケーションズでは、各業界に合わせた商圏分析の導入支援や、個別のご相談を承っております。人流データを活用した商圏分析にご興味をお持ちでしたら、ぜひお気軽にお声がけください。